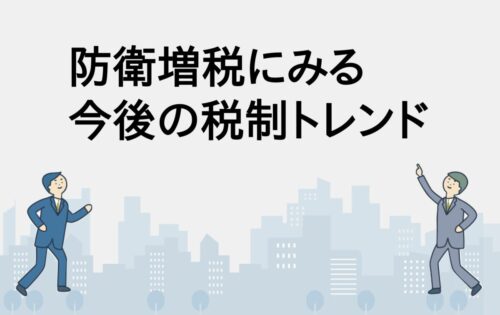103万円の壁の本質
2025年01月16日
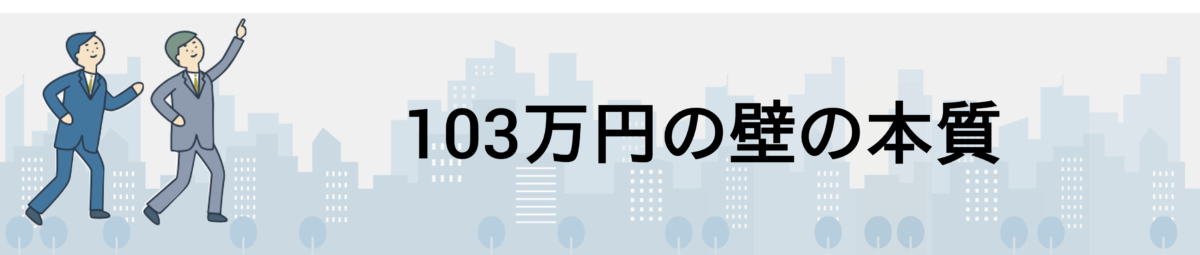
昨今、注目されている「壁」。
日本のパート従業員は、年収に応じて「税の壁」や「社会保険の壁」に直面しています。現状の制度を前提に話をすれば、年収が98万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税が課されます。
実際に、19歳以上23歳未満の学生は、年収が103万円を超えると、親の税負担が増加するため働きすぎを避けようとします。
この問題を解決するため壁を引き上げた場合、全所得層に対する所得控除額の拡大による減税となりそうです。
一部の会社では、支給される「配偶者手当」が打ち切られ、世帯収入が減少することもあるようです。
さらに、被保険者数51人以上の企業で週20時間以上勤務、かつ月8.8万円(年収106万円)を超えるなどで、社会保険への加入が義務付けられ、社会保険料負担により手取りが減少します。
106万円で保険料の徴収が始まり、125万円程度になるまで手取り額が減る状況が続くのです。
このため、多くのパート従業員は労働時間を抑える傾向になります。現在の制度では、働き控えをした方が労使双方の社会保険料の負担を抑えることができてしまうのです。
一言で「壁の解消」と叫ばれていますが、所得税減税による影響だけでなく、「103万円の壁を超えたら損」という思い込みだけで就労調整がなされている面もあります。
企業にとっては、所得税は減税になっても、社会保険料の負担増がのしかかってきそうなことも分かってご対処ください。
<この記事は、「経済リポート 2025年1/1号」に掲載されたものです>